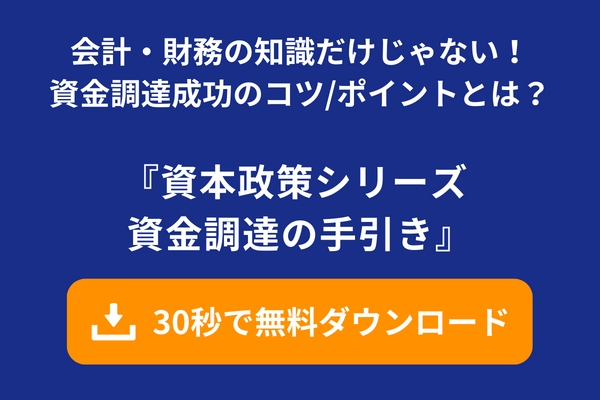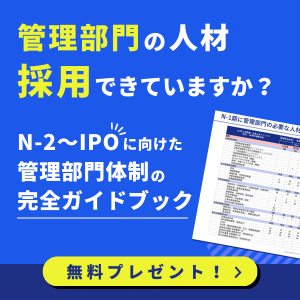COLUMN
コラム
法定監査とは?種類、任意監査や税務調査との違いを解説
執筆者:茅原淳一(Junichi Kayahara)



『資金調達の手引き』
調達ノウハウを徹底解説
資金調達を進めたい経営者の方の
よくある疑問を解決します!
企業経営の中で、監査が必要な場面が必ずあります。
監査は主に法令で定められている「法定監査」と、各企業が任意で実施する「任意監査」の2種類に分けられます。
本記事では法定監査について詳しく紹介します。
目次
法定監査とは

法定監査とは、法令等で義務とされている監査のことを指します。
法定監査は、通常は大企業に義務付けられている会計監査を指しますが、一方で法定税務調書の内容の正確性の監査も、法定監査と呼ばれる場合があります。
つまり、法定監査という言葉には2つの異なる意味があるため、それぞれの違いについてしっかり理解しておきましょう。
以下2つの違いについて説明します
①会計監査
②法定税務調書
法定監査①:会計監査
まずは会計監査についてです。
法定監査という言葉は、主に会計監査を指します。
会計監査は、企業が作成した財務諸表について、金融商品取引法及び会社法に照らし合わせた際に適正であるかどうかについて監査するものを指します。
監査結果については、独立監査人の監査報告書の中で、以下の4つの意見に分かれて公表され、企業は有価証券報告書や財務情報の中で示していく必要があります。
| 無限定適正意見 | 財務諸表に問題がなく、情報として適正である |
| 限定付適正意見 | 財務諸表の作成・表示の中で、一部誤りがある |
| 不適正意見 | 財務諸表の作成・表示について、不適正である |
| 意見不表明 | 財務諸表の適正が判断できない(監査が実施できないなど) |
会計監査を受ける必要がある企業については、以下のいずれかに当てはまる企業となります。
・資本金が5億円以上もしくは負債合計額が200億円以上の大会社
※委員会の設置がされているかいないかに関わらず、大会社は監査の対象となる。
・監査等委員会または指名委員会等を設置している会社
・会計監査人の任意設置をしている会社
なお、会計監査を請け負う機関については、監査法人と独立した公認会計士を挙げることができます。
会計監査の請負先1:監査法人
会計監査の請負機関としては、主に監査法人が担っています。
監査法人とは、公認会計士法に則り、会計監査を行うため設立された法人を指し、5人以上の公認会計士を社員として雇用している機関となります。
規模が大きい企業などについては、基本的に監査法人によって会計監査が行われていますが、コンサルティング業務等の監査業務には当たらない業務も請け負っている監査法人もあります。
なお、監査業務を実施するためには「独立性」が必須となります。
会計監査の請負先2:独立した公認会計士
監査法人だけでなく、個人の公認会計士によって行われる場合もあります。
監査業務を実施するうえで、公認会計士が1名でもいれば実施することはできますが、規模が大きくなってしまうと、なかなか一人で全てこなすことは困難です。
しかしながら、中小企業については監査法人ではなく独立した個人の公認会計士によって監査を行うことは可能であり、実際に会計監査を請け負っている公認会計士も存在しています。
会計監査の主な区分
会計監査については、いくつかの種類に分けることができますが、押さえておくべき2つをご紹介します。
・金融商品取引法に則った監査
・会社法に則った監査
金融商品取引法に則った監査
まずは、金融商品取引法に則った監査です。
さらに、「財務諸表監査」と「内部統制監査」に分けることができます。
・財務諸表監査:財務諸表(損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書)やその内容について正しいかを監査。
・内部統制監査:財務報告における内部統制の適正を監査。
なお、金融商品取引法上、有価証券報告書などに含まれている財務諸表は、公認会計士又は監査法人の監査証明を受けなければならないと明記されています。
会社法に則った監査
もう一つは会社法に則った監査です。
会社法では、大会社(資本金が5億円以上又は負債の部の合計額が200億円以上である株式会社)は、会社法第436条において、「定められている計算書類及びその附属明細書が適正に作成されているかについての監査証明を受けなければならない」と決められています。
監査証明を行うのは、その企業と特別の利害関係のない公認会計士や監査法人のみです。
法定監査②:法定税務調書の法定監査

法定税務調書の内容確認についても、「法定監査」と呼ばれる場合があります。
法定調書とは「法定調書合計表」を指し、年末調整の結果に基づいて作成され、毎年税務署に提出される書類です。法定調書を提出する目的は、税務署が納税者の正確な支払いを把握をするためです。税務署から法定調書についての調査が必要とされた場合、法定監査が行われる場合があります。
対象となる企業は、会計監査が義務づけられている大会社(資本金が5億円以上もしくは負債合計額が200億円以上)です。
法定税務調書の監査は会計監査とは異なり、基本的にはその企業の顧問税理士が請け負います。
法定税務調書の法定監査でよくある指摘事項
法定税務調書の法定監査で指摘される内容としては、書類の作成漏れなどがあります。
・パートやアルバイト社員の源泉徴収票の作成漏れ
・外部の委託先などに支払いを行った支払調書の作成漏れ
などが該当します。
その他にも、税務署へ提出すべき調書の作成漏れなどもありますが、2016年からマイナンバーの記載が必要となっていることから、マイナンバーの記載漏れがないかという点も指摘事項の一つです。
法定税務調書の法定監査タイミング
法定監査が実際に行われるタイミングとしては、例年と比較して、提出書類に大きな変化があったときに実施されることが多いです。
例えば、例年提出していた調書が大きく減った時や、同じ業種で同程度の企業規模である他社と比較して、提出された調書の種類に極端に差がある場合は監査が入ることが多いです。
また、特定の業界に対して税務署へ提出すべき調書の漏れを減らしていくために、特定の企業に法定監査が実施されることもあります。
業種や業態によっては、様々な調書の提出が必要とされることから、提出漏れが発生する場合もあります。そのため、こうしたミスを業界全体で抑制していくためにも、法定監査が実施されることがあります。
その他には、法律や規制の改定、基準の見直しなどにより、制度が変更した際に。その内容を周知していくため法定監査が実施されるケースや、特定の業種に対して重点的に調査して国税庁の方針により法定監査が実施されるケースもあります。
法定税務調書の法定監査の流れ
法定監査が行われる際の具体的な流れについては以下の通りです。
①税務署から法定監査実施についての連絡が電話で行われ、監査実施日の日程調整を行う。
②事業者へ、法定監査当日に必要とされる資料のリストが送付される。
※給与規程、従業員名簿、支払調書、過去3年分の源泉徴収票など)
③監査当日は、税務署の担当者から質問される会社の概要等について回答し、それぞれの内容を説明する。
④事前に連絡があった資料一式を税務署の担当者が確認し、質問があった場合は対応する。
⑤記入漏れの書類等があった場合は、それらのリストが渡されるので、記載された調書の再提出をする。
法定税務調書の法定監査と税務調査の違い
法定監査と混同しがちなものとして税務調査があります。
税務調査では、法人税や所得税など、企業として納めるべき税金が正しく納められているかどうか調査し、誤りがあった場合は是正するよう指示があります。一方で、法定監査で調査されるものは、税務署への提出書類が対象となります。そのため、法定監査による調査で、提出すべき書類に不備があった場合においても、税務署から税金の追徴等はありません。
法定監査で指摘があった場合は、正しい書類の提出が求められます。つまり、法定監査ではこれまでの提出書類における誤りを見つけ、今後正していくよう指導していくものとして行われます。
なお、法定監査から税務調査へ移行することは基本的にはありません。もし、源泉徴収等の漏れが発覚した場合は、納税するよう指導されることがありますが、自主的に不足分を納税すれば、加算税などは発生しません。また、万が一税務調査に移行するようなケースが生じた場合、必ず事前通知がされます。
法定監査と税務調査は似ているように思われますが、全く異なるものであるため注意しましょう。
法定監査と任意監査

法定調査とは別に「任意調査」もあります。
任意調査とは、法定調査以外の調査全体を指し、経営陣や株主の判断によって行う監査のことを指します。任意監査は法的に義務付けられてはおらず、「法律的な義務があるか否か」が、任意監査と法定監査の違いです。監査対象外となる中小企業等については、任意監査を実施するかどうかが各企業の判断によって異なります。任意監査は、内部統制の確立や自社の信頼を他の企業やステークホルダーに示すために実施されますが、任意監査を実施するためには多くの手間やコストが発生します。
任意監査を実施する際には、それぞれの企業における経営方針にあわせて検討していくようにしましょう。
まとめ
本記事では、法定監査の概要や任意監査、税務調査との違いなどについてご紹介しました。法定監査には様々な種類の監査が存在します。監査の実施は法令で定められており、企業運営において重要な役割を担っているので、それぞれの監査の意味やポイントをしっかりと理解しておくようにしましょう。
本記事が、企業の経営者やガバナンスに関わる担当者の参考になれば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。
法定監査に関連した、内部統制・内部監査については次の記事もご参照ください。
⇒法定監査とは?種類、任意監査や税務調査との違いを解説
⇒ISMS(ISO27001)内部監査とは?進め方、実施の注意点を解説
⇒ISO9001内部監査とは?目的、質問例、進め方を徹底解説
⇒内部監査報告書とは?目的や書き方、流れをわかりやすく解説
⇒内部統制監査とは?目的、内部監査/会計監査との違い
⇒内部統制実施基準とは?概要や2023年4月の改訂ポイントをわかりやすく解説
⇒内部統制システムとは?目的、義務がある会社、具体例をわかりやすく解説
⇒内部統制報告書とは?目的、提出義務がある会社、作成方法などを解説
また、コーポレートガバナンスについては、次の記事もご参照ください。
⇒コーポレートガバナンス(企業統治)とは?目的・強化方法・歴史的背景について解説
⇒コーポレートガバナンス・コードとは?概要・特徴・制定された背景について解説
⇒コーポレートガバナンス・コードの5つの基本原則|特徴・制定の背景・適用範囲と拘束力について解説
⇒【2021年改訂】コーポレートガバナンス・コードの実務対応と開示事例
⇒プリンシプルベース・アプローチ|ルール・ベース・アプローチとの比較・背景・意義について解説
⇒コンプライ・オア・エクスプレイン|コンプライアンスへの対応・意義・必要性について解説
スタートアップ・ベンチャーの経営をされている方にとって、事業に取り組みつつ資金調達や資本政策、IPO準備も進めることは困難ではないでしょうか。
財務戦略の策定から実行まで担えるような人材をを採用したくても、実績・経験がある人を見つけるのには非常に苦労するといったこともあるでしょう。
このような問題を解決するために、SOICOでは「シェアリングCFO®︎」というCFOプロ人材と企業のマッチングサービスを提供しています。
シェアリングCFO®︎では、経験豊富なCFOのプロ人材に週1日から必要な分だけ業務を依頼することが可能です。
例えば、ベンチャー企業にて資金調達の経験を持つCFOに、スポットで業務を委託することもできます。
専門的で対応工数のかかるファイナンス業務はプロの人材に任せることで、経営者の方が事業の成長に集中できるようになります。
「シェアリングCFO®︎」について無料相談を実施しているので、ご興味をお持ちの方はぜひ下のカレンダーから相談会の予約をしてみてくださいね!
この記事を書いた人
共同創業者&代表取締役CEO 茅原 淳一(かやはら じゅんいち)

慶應義塾大学卒業後、新日本有限責任監査法人にて監査業務に従事。 その後クレディスイス証券株式会社を経て2012年KLab株式会社入社。 KLabでは海外子会社の取締役等を歴任。2016年上場会社として初の信託を活用したストックオプションプランを実施。 2015年医療系ベンチャーの取締役財務責任者に就任。 2018年よりSOICO株式会社の代表取締役CEOに就任。公認会計士。