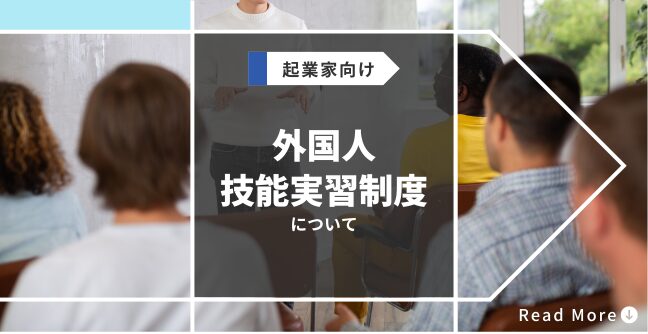
外国人技能実習制度について
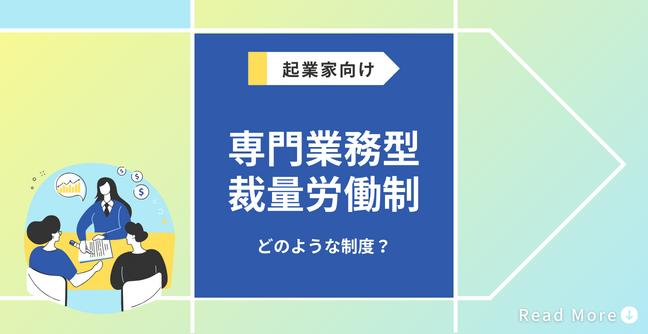
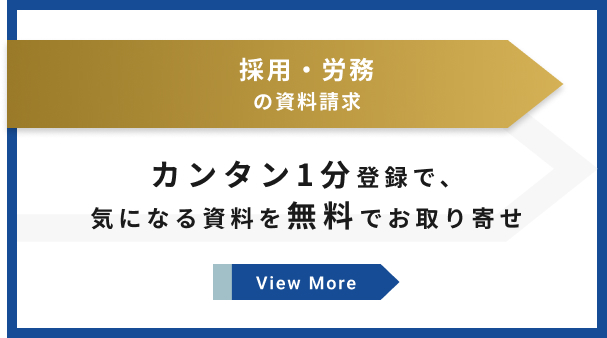
政府の「働き方改革」の進展で、働き方の選択肢が広がってきました。
近年、特に注目されているのが「専門業務型裁量労働制」です。
今回は「専門業務型裁量労働制」について、解説します。
目次
まず、「専門業務型裁量労働制」の「裁量労働制」の部分について見ていきましょう。
「裁量労働制」とは、基本的に「労働者が自分で労働時間を決められる」労働契約を指します。
簡単に言えば、実際に働いた時間が3時間でも10時間でも、8時間働いたと「みなされる」制度です。
この場合の8時間を「みなし労働時間」と言い、給与は8時間分が支払われます。
労働時間だけでなく、働き方もあなたの「裁量」にゆだねられるのです。
たとえば、お昼に出社して3時に帰ろうが5時に帰ろうがあなたの自由です。
働き方、つまり業務の進め方、やり方も自由に決められます。
与えられた業務の時間配分、手段や方法もあなたが勝手に決めていいのです。
つづいて「専門業務」の部分について。
「専門業務型」ですから、誰でもというわけにはいきません。
この制度を適用できる業務が限定されています。
「専門業務型裁量労働制」の法令では、その対象業務が非常に限定的です。
たとえばファッションデザイナーです。
8時間みっちり働いたからといって、よいデザインができるとは限りません。
家で本を読んだり、街をぶらぶらしたりする間にひらめくこともあります。
時間で拘束されたり、仕事の進め方を指示されたりしないほうが、かええって効率が上がることもあるでしょう。
このような業務が「専門業務型裁量労働制」の対象業務になっているのです。
詳しくは次項にまとめますが、研究者、編集者、映画やテレビの制作者、ライター、弁護士などの士業など、専門的な職業が該当します。
「専門業務型裁量労働制」では19の業務がその対象業務になっています。
概略は以下のとおりです。
(1) 新商品、新技術の研究開発または人文科学、自然科学に関する研究の業務
(2) 情報処理システム分析または設計の業務
(3) 新聞、出版の事業における記事の取材、編集の業務。「放送番組」の制作のための取材、編集の業務
(4) 衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務
(5) 放送番組、映画などの制作の事業におけるプロデューサー、ディレクターの業務
(6) 広告、宣伝などにおける商品の内容、特長などに関わる文章の考案(いわゆるコピーライター)業務
(7) 事業運営において情報処理システムを活用するための問題点の把握またはそれを活用するための方法に関する考案あるいは助言(いわゆるシステムコンサルタント)の業務
(8) 建築物内での照明器具、家具などの配置に関する考案、表現または助言(いわゆるインテリアコーディネーター)の業務
(9) ゲーム用ソフトウェアの創作の業務
(10) 有価証券市場における相場などの動向または有価証券の価値などの分析、評価またはこれに基づく投資に関する助言(いわゆる証券アナリスト)の業務
(11) 金融工学等の知識を用いた金融商品の開発の業務
(12) 大学における教授研究の業務(主として研究に従事するものに限る)
(13) 公認会計士の業務
(14) 弁護士の業務
(15) 建築士(一級建築士、二級建築士及び木造建築士)の業務
(16) 不動産鑑定士の業務
(17) 弁理士の業務
(18) 税理士の業務
(19) 中小企業診断士の業務
上記のとおり、専門性が高い職業が該当しています。
これから起業する人にとって会社設立は分からないことが多いのではないでしょうか。
また、起業したばかりの人にとっては事業の立ち上げと同時に様々な手続きを進めなくてはならず大変な思いをしている方も多いことでしょう。
そこで、ミチシルベでは
・「会社設立について相談したい・・・」
・「会社設立の手続きどうしたらいいかよくわからない・・・」
・「税理士や司法書士を紹介してほしい・・・」
といった起業したばかりもしくはこれから起業する方々のお悩みにお応えするべく、会社設立についての無料相談を実施しています。
下記バナーから無料相談をお申し込みできますので、ご自身の会社設立に関するお悩み解消にご活用ください。
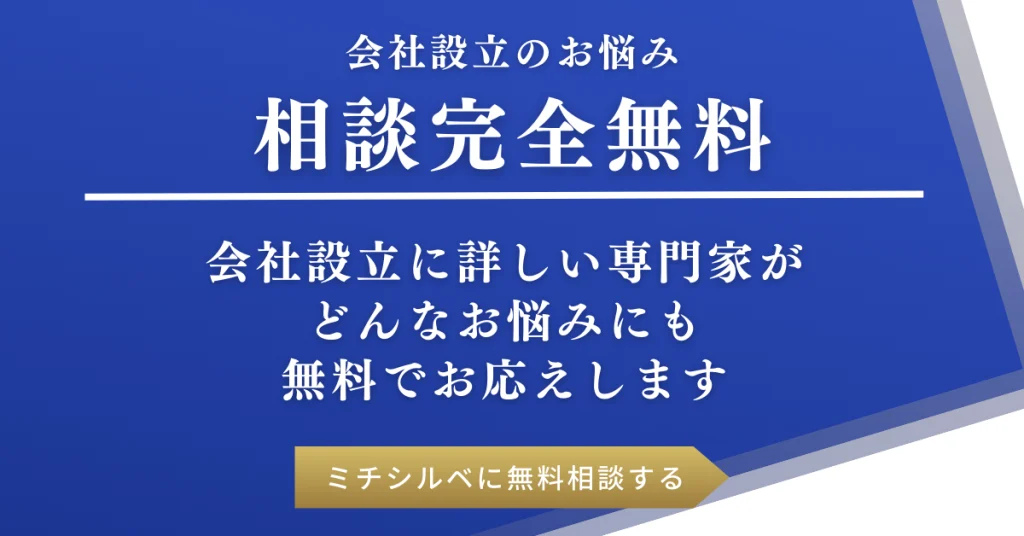
会社が専門業務型裁量労働制を導入した場合、待遇(労働条件)はどう決まるのでしょうか。
専門業務型裁量労働制は会社が勝手に決めるものではありません。
その導入にあたっては、「労使協定」の締結から所轄労働基準監督署長への届け出が必要です。
労使協定は会社と労働者の間で締結されるものです。
具体的には、従業員の過半数を占める労働組合、または過半数代表者との間で締結します。
これによって所定労働時間ほか、労働条件の細目が決定されます。
労使協定で規定されるのは主に次のような項目です。
・業務内容と対象従業員
・みなし労働時間
・時間外手当
・休日労働
・深夜勤務
・健康と福祉
・苦情処理
労使協定が定まれば、その協定に基づいて所轄労働基準監督署長へ届け出ます。
本社・支社などに分かれている会社なら、それぞれで届け出が必要になります。
「所轄」としているのは、労使協定も含め本社・支社などで個別に必要だからです。
労使協定で届け出する業務が定められますが、その業務範囲は前述の対象業務です。
しかし、業務名だけでは不明確なものもあります。
対象業務をもう少し詳しく見てみましょう。
たとえば「(2) 情報処理システム分析または設計の業務」にプログラマーは入るでしょうか。
この業務についての「附則」には、はっきりと「プログラマーは含まれない」と書いてあります。
一般に、プログラマーはシステムの分析や設計には関わらないとの認識によるものです。
プログラマーの方々から意義が出るかもしれません。
でも役割分担から言えば、プログラマーはソースコードを書くのが仕事です。
それ以前の要件定義から、システム設計は主にシステムエンジニアの役割となります。
また、放送や映画で、音響エンジニアやカメラマンも対象業務にはなりません。
ディレクターの指示によって業務を行うものとされているからです。
自分の「裁量」で動いてよい業務と、指示なしには動いてはいけない業務を分けているのです。
「専門業務型裁量労働制では残業代が出ない」と認識している方は少なくありません。
これは会社側にも働く側にもありがちな誤解です。
賃金は、まず所定労働日(週休2日なら、週5日)での労働時間で計算します。
この労働時間は当然ながら「みなし労働時間」です。
では1日の「みなし労働時間」を「労使協定」によって9時間とした場合は?
労働基準法による「法定労働時間」は1日8時間なので、残り1時間は時間外労働となります。
残り1時間については25%増しで計算します。いわゆる残業割り増しですね。
残業代分ではあっても、「みなし労働時間」の内ですので特に申請する必要はありません。また深夜勤務や休日勤務などでも割り増し賃金が支給されます。
ただしその場合には、通常事前に申請が必要となります。
労使協定によっては、労働基準法による割り増しよりも高く設定されることがあります。
専門業務型裁量労働制は、専門的な仕事をする場合に採用されていることが多い制度です。
自由な働き方ができるメリットがありますが、オンオフの切り替えがしにくい、働きすぎてしまう、労働時間と給与がマッチしないなどの問題もあります。
この制度の運用を考えている経営者、またはこの制度で働くことを検討している人は、メリットとデメリットをよく考えることが大切です。
この記事のキーワード
キーワードがありません。
この記事を見た方はこんな記事も見ています
この記事と同じキーワードの記事
まだ記事がありません。
キーワードから探す



カンタン1分登録で、気になる資料を無料でお取り寄せ



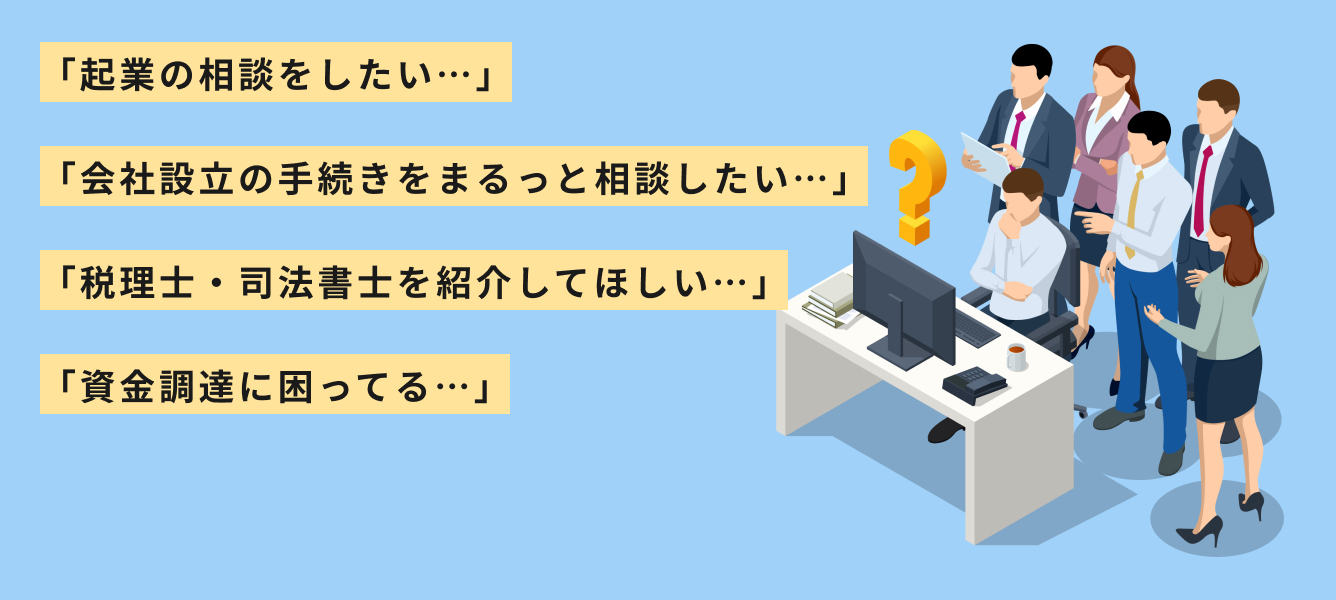
そんなお悩みをお持ちの方は、まずはお問い合わせください!